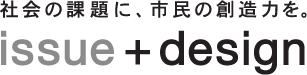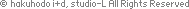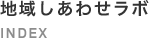
しあわせ地域ケーススタディ03 大野市
![]()
お互いを支え合う文化、“結の心”が自然と根づいた町
![]()
福井県大野市。荒島岳など、周囲が1,000メートル級の高い山々に囲まれた盆地形となっており、冬は福井県内でも有数の豪雪地帯だ。そういった環境がおいしい水を育み、今だ生活用水の8割が地下水という、全国でも稀な「名水の町」である。米やそば、里芋などの農産物や日本酒が有名なのは、そのおいしい水による恩恵が大きい。また、山頂にそびえる大野城と短冊状に区切られた街並み、中世から近世にかけて築かれた寺院が連なる寺町通り、400年以上続くといわれる七間朝市など、歴史を感じさせる景観から「北陸の小京都」とも呼ばれている。高い山々に囲まれた盆地、豪雪地帯ということが大きく影響し、外からの移住者も少なかったことから、大野は独自の文化、地域性を育んできた。
![]()
「Cafe Name came Ono」経営者で福井市出身の二見祐次さん(50歳)は、大野に住む人たちの人間性に魅了された一人だ。「大野の人は穏やかなんです。喧嘩や争いごとも見たことがない」。食品卸売会社の会社員をしていたときに福井県中を営業でまわっていたが、商品の在庫を切らしたときなど、取引先に叱責罵倒されることは日常茶飯事。しかし、大野市内の取引先は、「どんならんな(どうにもならないな、仕方ないね)」と拍子抜けするぐらい、おおらかな返答なのだという。
![]()
「大野の自然の雄大さが影響しているのか、懐が深いんですよね。なんでも受け入れてくれるというか、前向きというか。自分の利益優先で動くような人がいない。商売していて同業者に対してもライバル意識がないんです。“あなた同業者なの?じゃあ、一緒にやろう”って。ガツガツしていない。協力し合う文化、助け合う文化、“結”の気持ちが根づいているんです」。
![]()

![]()
そのことを裏付けるエピソードがある。グラフィックデザイナーで、イベント企画などを手がける長谷川和俊さん(30歳)は、ミュージックフェスティバルを企画したとき、他の団体のイベントと開催日が被ってしまった。「そういう時って、集客ができないようにイベントを妨害したりする人たちもいるみたいなんですが、“イベントを一緒にしてしまったらいいんじゃない?”と先方が提案してくれて、同時開催しました」。
![]()
長谷川さんは生まれも育ちも生粋の大野人。「大野がどうやら特別らしい」と気づいたのは、市外から来た人たちの言葉からだった。
![]()
「水がおいしい、食べ物がおいしい。人がやさしい。自然が豊か。周りのことは気にせずマイペース。フリースピリット──。全部、自分たちには当たり前のことだったけど、それが実はスペシャルなことだった。誰かが困っていたら、すぐに人が集まって助け合う。そういう大人たちを見て育っているから、自分たちも自然とそうなった。みんなそんな大野が大好きだし、大切にしたいし、自慢したいんです」。
![]()
ミュージックフェスティバルに参加してくれたミュージシャンたちも、そんな大野の自由な雰囲気、素晴らしい自然環境、おいしいご飯に感動して、大野のファンになるそうだ。「今度はいつ呼んでくれるの?」と問い合わせが絶えないんですよ、と長谷川さんはうれしそうに笑う。
![]()
![]()
“地域おこしイベント”も自発的にみんなで協力し合って開催
![]()
市役所に勤める、雨山直人さん(31歳)は、大野のソウルフード「とんちゃん」(ホルモン焼き)を愛してやまない若者の集まり、「越前おおのとんちゃんを愛でる会」の創立メンバー。「とんちゃん祭」を5年連続開催、全国からホルモン好きが集まり、知名度もどんどんあがっている。雨山さんのような市役所の若手職員たちが「仕事」という感覚を抜きにして、 自発的に“地域おこし”を率先して行っているのも大野では特徴的といえる。
![]()
そのほかにも、福井の新しい名物「醤油カツ丼」を広めるべく、「世界醤油カツ丼機構」を設立したメンバーの一人も役場職員だ。市役所の上司や先輩たちの理解や後押しがあり、若い人たちが“やりたい”と思って行動したことに対して、協力を惜しまないのだという。
![]()
それは市役所だけのことではなく、大野で脈々と引き継がれてきた、若者と年配者との友好な関係性といえる。「おんちゃん(おじさん)たちが元気ですからね!こっちが負けているぐらいです」と雨山さん。その元気が若い人たちの目標になり、指針となり、頑張りにもつながっている。
![]()

![]()
コーヒーショップ「モモンガコーヒー」の店主、牧野俊博さん(34歳)は高校卒業後、東京の大学に進み、そのまま大手電機メーカーに就職した。「何もない大野がずっと嫌いだった。母が体調をくずしたことをきっかけに帰郷したんですが、何でもある東京にもどりたくて仕方がなかった」。
![]()
そんな時、何気なく訪れたのが、前述の「とんちゃん祭」。自分とあまり年齢の変わらない若者たちが主宰していたことに衝撃を受けた。「こんなこと、実現できちゃうんだって驚きました。みんな一生懸命で、とても楽しそうで。もしかしたら、大野ってすごいんじゃないかって」。そんなとき、「とんちゃん祭」主催者の一人から「ワークショップをするからよかったらおいで」と誘われた。「大野をどんな町にしたいか、みんなで話し合ったんです。マッキー(牧野さん)は何をしたいの?って言われて、“僕は大野でコーヒーショップをやる”って、みんなの前で宣言しちゃった(笑)。そしたら、“応援するよ〜!”ってみんなに背中を押された感じです」。
![]()
牧野さんは大学時代に喫茶店でアルバイトし、ドリップで入れたコーヒーのおいしさに開眼、以来、大のコーヒー好きに。「大野は水がおいしい。この水でコーヒーを淹れたら、おいしいコーヒーになるに違いない。城下町の名残がある、七間通り周辺に店を出せたらなぁ」と漠然とイメージしていた時だった。それまで大野には自家焙煎のコーヒーショップはなかった。 それからというもの、ワークショップで知り合った人たちからどんどん友人の輪が広がっていき、5月に「モモンガコーヒー」がオープンするまでいろんな人が手を貸してくれた。小さな町だから、あっという間につながるのも大野らしい。町なかにこだわり、場所は六間通りと五番通りの交わるところにした。
![]()
「いろんな人たちが訪れてくれて、恐いぐらいに順調です(笑)。先日も東京からわざわざ、ここを目指して来てくれて。それも周りの助けがあったからこそ。駐車場からちょっと歩くんですけど、町の風景を楽しみながら歩いてきてもらうのもいいかって」と牧野さん。
![]()
![]()
おんちゃん(おじさん)たち 先輩が築いた、音楽を愛する環境
![]()
自由なマインドを持ったおんちゃん代表なのが、島田健一さん(62歳)だ。島田さんは「ハロー音楽舎」という音楽のPA(電気音響設備のエンジニア)ボランティア集団を70年代に結成した。イベントをしたくても音響を管理できる人がいなかったからだ。音楽好きが集まった「ハロー音楽舎」だが、音響に関しては素人ばかり。資金がないのでスピーカーも当初は手作りしていた。
![]()
「ハロー音楽舎」があるおかげで、大野の人たちにとってイベントを開くことは特別なことではない。主婦だって、若者だって気軽にイベントを開くことができる。前述のイベントの企画を手がける、長谷川さんも島田さんを頼りにする一人だ。「ほとんど利益にならない活動を続けていく理由は?」と島田さんに聞くと、「 “(イベント行って)楽しかったねぇ”という、来てくれた人の笑顔ですね」と笑う。
![]()
そんな島田さん、お願いされると「NO」といえない性格で、「なんとかしよう!」とイベントを引き受けすぎてしまうことがある。そんなときは、「ハロー音楽舎」のスタッフやOBが総出で集まって対処するのだそうだ。「40年近くも続けてこられたのは、こんな自分につきあって周りが手伝ってくれたからです。本当にありがたい」と島田さん。
![]()
大野では、昔から田んぼの田植えや稲刈りのシーズンになると、人知れず人が集まってきて、助け合うことが普通だった。そういった結の心の精神が大野の人のDNAに深く根づいている。だからこそ、今でも困っている人がいれば、手を差し伸べ(押し付けがましくないのが大野人)、頼みごとにも快く応じてくれる(私なんかでお役に立つかしら?と、どこか遠慮がちなのも大野人)。
![]()

![]()
「大野ってやっぱりどこにもない場所。市外に出るとたまらなく愛しくなって、帰ってきたくなる。福井県人、というよりも大野人という意識が強くなりました」と鉢植えアーティストの髙見瑛美さん(29歳)。
![]()
福井市内で働いていたときに、実家の山が恋しくなり、子どもの頃に山で遊んだ経験が、なによりも貴重な体験だったと気づいたそうだ。いまではそんな経験を生かし、山ブドウやいちぢく、ムベなど山の四季を感じさせる木々の鉢植えを制作するようになった。
![]()
そんな、大野を愛する人たちがたくさん住んでいる町は、平和な雰囲気に満ちあふれている。