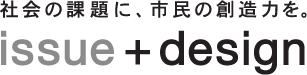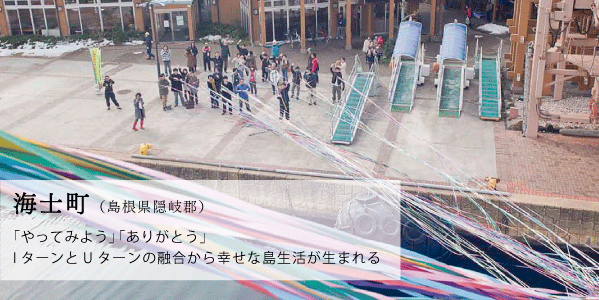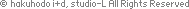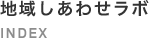
しあわせ地域ケーススタディ01 海士町
離島のハンデのために人口激減、少子高齢化が深刻に
島根県の北60キロ、日本海に浮かぶ隠岐諸島の中のちいさな島にある海士町。後鳥羽上皇が流された流刑地としても有名で、神楽や俳句など歴史文化や伝統が残る一方、島すべてが国立公園に指定されるほど自然が豊かな場所だ。島根県・七類港と鳥取県・境港から高速船で 2時間弱、フェリーなら3〜5時間ほどかかる。そんなまさに陸の孤島とも呼べる海士町に、島外からひっきりなしに移住者がやってくる。しかも年齢は20〜40代という、働き盛りの世代だ。
![]()
海士町から本土までの60kmという距離は、産業や日常生活でさまざまなリスクを生み出してきた。周りの海ではアワビやサザエ、イカ、四季折々の魚介類が豊富に獲れるのだが、朝獲れたものを本土の魚市場までフェリーで運ぶと当日のせりには間に合わない。せっかくの魚介類は鮮度が落ちた状態で次の日の市場に並び、値段は買いたたかれ二束三文、漁の燃料費がかさむだけで、儲けはほとんどでない。また島には高校が1つしかなく、大学に進学したい子どもは本土の進学校へ下宿して通うのが常だった。たとえ島の高校に通ったとしても、大学も専門学校もないから、大抵の若者は島を出ることになる。彼らのほとんどは島に戻らない。島での就職先を見つけるのが難しいからだ。
![]()
そんな離島の抱える問題が原因となって、昭和20年に7000人いた人口は現在では約2400人に激減。年間に産まれる子どもは約10人、人口4割が65歳以上という、超少子高齢化の過疎の町である。
![]()

20〜40代の働き盛りの若者が次々と移住
平成15年に町長になった山内道雄氏が行った改革はさまざまあるが、そのなかの一つにUターン・Iターンの定住促進がある。「島が生き残る」ために人口の流出に歯止めをかけながら、流入を促す目的だ。定住用の住宅を新たに建築、空家になっている家屋をリノベーションするといった住宅対策を行った。また、生計の手段を確保できるように、産業創出も促した。たとえば、島で農業をしようとしている人を農業研修生として受け入れて就農支援を行ったり、役場の臨時職員として雇い入れたり、また、島外の人に島の商品価値のあるものを発見してもらう「商品開発研修生」といった制度も導入した。
![]()
島の民間の新しい産業である、第三セクターの「ふるさと海士」や隠岐牛の「隠岐潮風ファーム」、それに定置網漁、島の診療所などでも雇用枠を広げることに。そういったさまざまな対策を行った結果、361人のIターン(2012年度末)が島に移住するなど大幅に増加することになった。
都会にないものを求めて移住するIターン
海士町に集まるIターンは、ただ「田舎暮らしがしたい」という目的でやってくるのではない。前述の商品開発研修生や、集落支援員など、やりがいのあることを「やってみよう」という、目的意識のある人たちも多い。20〜30代が中心なのも特徴だ。
![]()
掛谷祐一さんは24歳のとき、町が募集していた農業研修生に応募し、単身で大阪から海士に移住した。畜産に興味がわいて、海士ファンバンクという島外からの出資を募る制度を利用し、牛を購入。わからないことは島の畜産関係者に聞いた。年に島内で3回行われる子牛のせりや、お産の立ち会いにも馴れた。最初の年は2頭の飼育からはじまったが、8年目の現在、飼育しているのは親牛20頭。町内の和牛改良組合の役員でもある。「最初はゼロからの挑戦でした。大変でしたけど、役場はもちろん、町のいろんな人に助けてもらって。今後は恩返しじゃないですけど、海士の畜産を発展させるためにできることを考えていきたいと思っています」と掛谷さん。
![]()

![]()
海士町の自然環境を生かし、起業した若者もいる。「大学を卒業したら、食に関わる仕事をしてみたかった」という、群馬県出身の宮崎雅也さんは、一橋大学在学中の夏休みに海士町を訪れ、民宿「但馬屋」の“じっちゃん”こと宇野茂美さんの、あまりのスーパーマンぶりに驚いた。民宿、畳屋、渡船の船長、なまこ加工品生産者、農家……といくつも肩書きがあったのだ。「すごい生命力を感じたというか、直感的にこの人からいろいろ学びたい!と思ったんです」。大学を卒業後、「但馬屋」の従業員として働き、船舶の免許も取得。田んぼや畑では無農薬の米や野菜を育て、ニワトリの世話もする。
![]()
「海士町は小さな島のなかに山があり、周りに海がある。山の栄養が海に流れ込んでおいしい魚が育つ。ここではその自然界の循環を間近で見ることができる。島の人たちは自然に寄り添って生きていて、その知恵がすごい」と宮崎さん。数年前には「但馬屋」と共同で干しなまこの加工会社を立ち上げ、品質がいいと評判となり、香港に上顧客を持つまでに。なまこの卵巣から作る珍味ばちこやこのわたも商品化した。そして現在、椿油のビジネスも思案中。じっちゃんは宮崎さんが来てくれたことで、若い戦力が加わり、ますますパワーアップしているそうだ。
移住者に刺激され、地元出身者の意識に変化
Iターンの移住者が増えるようになって、大きく変わったのが、地元やUターンの若者の意識だ。最初は、「よそ者が来て、勝手になにかやっとる」と遠巻きで見ていたものの、「町のためにやってくれとるのか」と一緒に活動する場面も多くなった。住民参加で話し合いを重ねて作った、10年間の「総合計画書」のなかでも、「支えあってくらそう」という項目がある。地域内外の住民の支えあいの推進だ。
![]()
下水処理事業を営む中村誠さんは、浄化槽点検で家をまわるとき、電球を変えたり、買い物を手伝ったり、独自で「なんでも10分サービス」を行って高齢者の生活をサポートしてきた。孤立していく集落の高齢者のために何かしなければという問題意識もあって、集落支援員のメンバーに。IターンとUターンを含む地元のスタッフで構成されている集落支援員は集落で困っていることをヒアリングし、問題解決のために地元の人たちと一緒に考え、内容によっては役場に提案するような働きをしている。
![]()
中村さんは当初、活動に消極的だったものの、今では地域の人とIターン集落支援員をつなぐ頼りになる兄貴として、欠かせない存在だ。「海士町の未来のためによそのもんががんばっとんのに、地元のわしらがやらなければ」と中村誠さん。
![]()

![]()
「なかむら旅館」の若主人、中村徹也さんは大阪の専門学校で料理を学び、松江のレストランなどで働いた後、島に戻ってきたUターン組。2013年の春、地元の人たち、Iターンらも手伝って、「音つなぎ 隠岐島前アコースティックフェスティバル」を、海士町のある中ノ島、西ノ島、知夫島の3島合同で開催した。
![]()
「地元の人間だけだとできることに限界がある。いろんな経験を経てきたIターンには、自分たちに出せない知恵やアイディアをもっている。彼らの存在は心強い」と中村徹也さん。フェスティバルのチラシのデザインはどうするか、アーティストの出演依頼はどんな文面でお願いすべきなのか、全国に告知をするのはどうしたらいいかなど、何から何まで初めてのことで、みんなで相談し、協力し合った。そして、開催期間10日間、通しチケット9,800円、参加有名アーティスト30組という、前代未聞の伝説のフェスティバルが実現したのだ。
![]()
海士町の住民は島外からのゲストに馴れっこだ。島民の中では、子どもから高齢者まで、初めて会う人にも「こんにちは」というのが当たり前。その和やかな雰囲気にミュージシャンたちは大感激したという。「素人集団の手作りフェスでアクシデント続きだったけど、そこがいいって言ってくれて。出演者の中には島が居心地がよくて、出番が終わってもいつまでも帰らない人もいたぐらい(笑)。次回も必ず呼んでくれっていわれました」。
![]()

![]()
Iターン移住を推進していった、「あいさつをする」という島の取り組みが定着した結果だ。
![]()
Iターンは島から脈々と受け継がれてきた生活の知恵を島民から学び、島民はIターンから労働力やアイディアを得る。お互いが刺激を受け合って、協力し合い、島のしあわせにつながっていくことを実現していく。
![]()
年に一度の大きな祭り「キンニャモニャ祭り」では、地元はもちろん、Uターンも、Iターンもすべての人が民謡キンニャモニャを踊る。子どもから高齢者まで、島民のほとんどが一斉に町を闊歩して踊る姿は圧巻だ。そこには、島民か、島外から来た人かどうかということは関係ない。海士町ではすべての人たちが協力して、豊かな暮らしを目指す土台ができつつあるのだ。